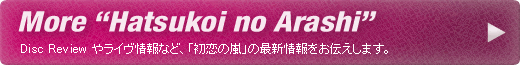SPECIAL ISSUE Vol.1

> Vol.1 > Vol.2 > More “Hatsukoi no Arashi”
ワンマンライヴ”Storm of
Last love”を11月29日と12月1日に控えた初恋の嵐。
ボーカル西山達郎の急逝から10年を迎えた今、彼らの辿った足取りに迫る

ぼんやりとしたモラトリアムの時代に初恋の嵐は鮮やかにやってきた
 2000年に入って間もない頃、初恋の嵐という座りのよいような、悪いような、なんとも青春の胸騒ぎを思い起こさせる名前のバンドを知った。
2000年に入って間もない頃、初恋の嵐という座りのよいような、悪いような、なんとも青春の胸騒ぎを思い起こさせる名前のバンドを知った。
何事もなく世紀末を超え、ぼんやりとした日々がずっと続いていきそうに思えた”あの頃”。はっぴいえんどが再評価されるなど”フォーキー”という言葉がある界隈では盛んに使われていた。
1960年代後半から70年代半ばにかけてのカルチャーへの憧れと逃避がこめられたこの曖昧な気分が、思春期の執行猶予を解決してくれることは、もちろんない。でも、多くは気が付かないふりをしながら、モラトリアムの刹那を自分たちだけのユースカルチャーとして楽もうとしていた。
そんな中、初恋の嵐は唐突にやってきた。まるで倦怠を吹き飛ばすような荒々しさと、冬を耐えた生命が芽吹き始める瑞々しさを携えた三月の空のように。
恋に笑い、恋に泣き、仲間と騒ぎ、不敵で無鉄砲で、どことなく不安で……
といった青春の特権を、誇らしくもほろ苦く言い当てたネーミングはとても鮮やかだった。(残念ながら)表現のレベルに至らない日記、私小説もどきのような「僕の歌」ばかりを歌うバンドが多い中、初恋の嵐は新しい風を吹き込んでくれそうな予感を抱かせたのだ。
素晴らしくも平凡な青春映画のようだった若者についての話
 初恋の嵐のボーカル、ギター、ソングライティングを担う西山達郎は、いつの時代も熱心に見続けられる素晴らしくもありきたりな青春映画から抜け出してきたような若者だった。それは、小さな映画館の片隅で、深夜のワンルームで、あるいは親が寝静まった後の居間で、平凡な若者が密やかに心を震わせ、語り継いできた類いの映画だ。例えばピーター・ボグダノヴィッチの『ラスト・ショー』のような。
初恋の嵐のボーカル、ギター、ソングライティングを担う西山達郎は、いつの時代も熱心に見続けられる素晴らしくもありきたりな青春映画から抜け出してきたような若者だった。それは、小さな映画館の片隅で、深夜のワンルームで、あるいは親が寝静まった後の居間で、平凡な若者が密やかに心を震わせ、語り継いできた類いの映画だ。例えばピーター・ボグダノヴィッチの『ラスト・ショー』のような。
彼は冗談が好きで、あまのじゃく。朗らかでハンサム。終わらないモラトリアムと戯れる”永遠の若者”といった雰囲気をまとった人気者だった。彼といると不安を先送りできそうな気持ちになった。「このままで楽しい日々が続くんだろうな」と。それはモラトリアムの幻想に過ぎないのだが。
一方で彼には、心の奥底を簡単には覗かせないかたくなさがあった。初恋の嵐のターニングポイントとなったシングル曲であり、若き愛の絶望を歌い切った「Untitled」を初めてライヴハウスで耳にした時のこと。彼に具体的なフレーズをあげて、「すごい歌詞だね」と感嘆しながら言ったことがある。彼の返事は「そんなこと歌うはずないじゃないですか。きっと聴き間違いですよ」。いつも通りの憎たらしくてチャーミングな笑顔があった。きっと自分の尻尾を掴まれることがたまらなく嫌だったんだろう。
彼は快活だったがどこか冷めていた。だからあまのじゃくだったのかもしれない。青春の光と闇、愛憎、モラトリアムにこんがらがったもどかしい日々、そこから抜け出せない自分をも切り裂かんとする鋭さがあった。得体の知れない凄みがあった。人生にもがく危うさがあった。彼の中では、99パーセントの諦めと1パーセントの希望がぎりぎりのバランスで成り立っていたように思えてならない。ただ、そんな怖さを秘めながら、仲間思いの優しい男だった。
いざライヴとなると彼は愛憎と真正面から組み合うガッツのあるギタープレイと声を聴かせてくれた。そこにはただならぬ迫力があった。向こう見ずな色気があった。(彼は冗談めいて「僕の声は最高なんですよ」とインタビューで応えたことがある)。また、彼の作る歌は力強く美しかった。同時に「僕はこのままで大丈夫ですか?」。そう祈っているようにはかなさがあった。彼の心のゆらぎはとてもリアルで、大人たちはどうであれ、彼と同じくらい年齢のお客さんたちは「これは自分たちのことを歌っている」と一聴して気付いたに違いない。彼は世代のぼんやりした曖昧さを引き受け、逃げ隠れすることを拒否しようしていた。まるで「例えだらしない青春でも、だらしないヤツらでも、ここが居場所なんだ。」とでも言っているかのように。
彼を知る者はみな友達になりたがった。バンド仲間の先輩たちは競うように彼を可愛がっていた。当然だと思う。彼が体現する青春の群像劇はとても魅力的だったから。みな彼の中の登場人物になりたかったのだ。
(初恋の嵐のバンドアンサンブルはよくニール・ヤングやジミ・ヘンドリックス、ビートルズ、バッドフィンガーを引き合いにされることが多かった。それは荒ぶる感情と直結したかのような人肌感を持つロックサウンドを、当時の彼らがチョイスしたのだろう、ということで、ここでは止めておきたい。その後の姿を見る機会は失われてしまったがゆえに……)
いつの時代にも響く”生きていくという物語”
 2000年から2001年にかけてMULE
RECORDSからミニアルバム『バラードコレクション』とシングル「Untitled」を発表した初恋の嵐は、時期を待たずに音楽業界から熱い注目を集める。争奪戦の末、2001年の秋にメジャーのレコード会社と契約。2002年春のメジャーデビューに向けアルバムの制作準備に入った。
2000年から2001年にかけてMULE
RECORDSからミニアルバム『バラードコレクション』とシングル「Untitled」を発表した初恋の嵐は、時期を待たずに音楽業界から熱い注目を集める。争奪戦の末、2001年の秋にメジャーのレコード会社と契約。2002年春のメジャーデビューに向けアルバムの制作準備に入った。
この頃、西山達郎の顔つきはあきらかに変わった。”永遠の若者”に別れを告げ、大人の顔になろうとしていたというか。甘く感傷的なモラトリアムの幻想から抜け、自ら作り上げた青春映画の幕を降ろそうとしているように感じた。代表曲「涙の旅路」で歌われる別れと新しい旅立ちをそのままに。
2001年の暮れに、新宿ロフトの楽屋で彼に会った。彼はトレードマークの銀フレームの眼鏡をしていなかった。この眼鏡は彼のこだわり、かたくなさの象徴だと思っていたのでわけを尋ねてみた。戻ってきた返事は「大宮でラジオの公開生放送をやったんですよね。女子高生たちがずっと見てたから、俺、モテるなって思ってたら、ブースを出た途端に聞こえたのが、なんかキモイ〜。ショックですよ。で、眼鏡を外しただけなんですけどね」。以前「Untitled」の歌詞について話をした時と同じような人懐っこい表情で笑っていた。
すぐに嘘だとわかった。彼はいつになく毅然とした目つきをしていたからだ。そこからは次の世界に歩を進める決意が伺えた。それでいてたくさんのものを捨ててしまったような、どことなく不安で寂しそうな顔をしていたのが印象に残っている。
この頃、彼の才能に魅せられていた多くは、彼がジャンルやコミュニティを越えた、スケールの大きなスタンダードソング(国民的なヒットソングと言ってもよいが)を作るはずだと期待していた。いよいよ、皆に等しくある人生、そこで揺れる”ひとりの感情”を”みんなの歌”として通用させるマジックをみせる時が来るのだ、と。
生前の西山が残したインタビューに「いつかミュージックステーションに出たい。タモリの場所でロックを鳴らせるまでは頑張る。そこに行かないと後は全部一緒みたいな気がする」という発言がある。彼はわかっていた。そして願っていた。”みんなの歌”を歌いたいと。
しかし2002年3月2日、『初恋に捧ぐ』のレコーディング中に彼は帰らぬ人となってしまう……
初恋の嵐は、ファンと共に年齢を重ねながらその人生に寄り添い、キャリアの節目節目で新しいファンを作る大きな存在になる可能性を秘めていたと、今でも思っている。
彼の歌は、あの時代も、今も同じリアリティをもって響いてくる。見たこともない風景が写った、見知らぬ誰かのフォトアルバムが心に響くように。いつの時代の誰にでもある”生きていくという物語”が刻まれた歌なのだから。その素晴らしさは、彼の没後10年目に、スピッツが「初恋に捧ぐ」のカバーを『おるたな』に収録したエピソードからも伺えよう。(天国で彼が「でしょ。俺さすがだな。スピッツはわかってるよね!」と冗談めいて笑っている声が聞こえるようだ)。
2011年、彼が次の舞台に向かう仲間として共に歩もうとした隅倉弘至(ベース)と鈴木正敏(ドラムス)は初恋の嵐の活動を再開させた。しばらくの間歩みを禁じられた彼の歌は再び鳴り始め、未完の物語が幕を開けようとしている。
Profile
初恋の嵐
西山達郎(Vocal&Guitar)2002年3月2日没(享年25歳)/隅倉弘至(Bass)/鈴木正敏(Drums)
2000年に『バラードコレクション』、2001年に『Untitled』をMULE
RECORDSからリリースし評判を呼ぶ。しかしユニバーサルミュージックからのデビューを目前にした2002年3月2日、西山が急逝。隅倉と鈴木は制作途中にあったレコーディングを続行し、7月に『真夏の夜の事』、8月に『初恋に捧ぐ』をリリース。2011年よりゲストボーカルを迎える形でライヴ活動を再開させている。
詳細なBiographyはこちら /hatsukoi/biography/